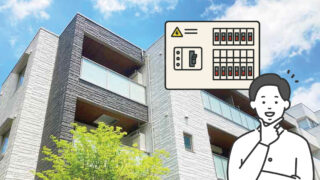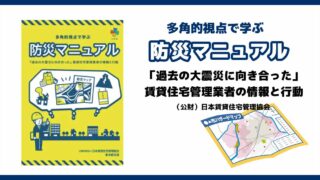感震ブレーカーは地震の揺れを感知して自動で電気を遮断する装置です。通電火災を防ぐため、地震後の火災リスク軽減に効果的です。特に避難時に電源操作が難しい場合や、高齢者・老朽住宅には設置が推奨されます。
【地震後に潜む火災リスク】通電火災とは?
地震による火災の中でも注意が必要なのが「通電火災」です。
これは、地震で停電した後、復電のタイミングで壊れた配線や電化製品から火災が発生する現象です。
たとえば、電気ストーブやこたつなどがスイッチオンのまま停電し、そのまま放置されていると、復電時に突然作動し、可燃物に引火する危険があります。
実際、阪神淡路大震災では火災の約6割が通電火災だったと言われており、東日本大震災や2024年の能登半島地震でも、避難後の住宅が通電火災により全焼するケースが相次ぎました。
なぜ通電火災が発生するのか
2024年1月1日に発生した令和6年 能登半島地震においても、通電火災は大きな課題となりました。消防庁・石川県の発表によると輪島市や珠洲市などで発生した住宅火災のうち、通電火災と推定されるケースが事実複数確認されています。
震災直後ではなく、復電が始まった2日後〜5日後に集中しています。地震によって電気が遮断され、その後復旧時に破損した配線・機器から火災が発生したとみられる事例です。
| 通電火災が起こりやすい状況 |
|---|
| 古い家屋や老朽化した電気配線 |
| 高齢者が多い地域で電気機器の電源を切らずに避難 |
| 復旧作業前に電気設備の点検をせず復電 |
| 避難時に主幹ブレーカーを落とさなかった |
いずれにしても被災直後に電気は大元で遮断しておかないと後日復旧時にはコンセントが繋がったままかもしれません。
このように従来の震災における通電火災の報告が多かったのにも関わらず、感震ブレーカーの設置率は極めて低かったとされます。
感震ブレーカーの種類と費用
感震ブレーカーは費用も様々です。利用者が自分で設置できるものから工事により建物全体の通電を一揆に遮断してしまうものまで多々あります。
建物オーナー様の立場からすると、万が一の際に入居者任せで感震ブレーカーが確実に作動するかどうかには不安が残ります。そこで当社では、数ある機種の中から、分電盤に内蔵されるタイプの「感震ブレーカー」をおすすめします。
このタイプであれば、建物全体の電気を自動で遮断でき、入居者の操作を必要としません。
設置にはブレーカーの交換費用を含めて10数万円程度かかりますが、通電火災から建物全体を守れることを考えれば、非常に高いコストパフォーマンスを発揮します。
通電火災を防ぐ感震ブレーカー、普及が進まない理由
通電火災を防ぐ有効な手段として注目される感震ブレーカーですが、実際の設置率は非常に低いのが現状です。その理由として、費用面の負担や認知度の低さ、自分で設置できる簡易タイプと分電盤型の違いが分かりづらいことなどが挙げられます。しかし、大切な建物や入居者を守るためには、建物全体の電気を自動遮断する分電盤型の導入が効果的です。災害時の備えとして、ぜひ一度ご検討ください。
| 必要性が知られていない | 「通電火災って何?」と聞く人も多い状況です。「通電火災」についての理解が必要です。 |
| 後回しにされがち | 防災グッズは買っても、ブレーカーのことは忘れがち。大元から電源を切らないと火災リスクは減りません。 |
| どれを選べばいいかわからない | 工事が必要なのか、どれが安心なのか不明で買わない人が多い。ネットで調べても種類は様々です。 |
| 価格面のハードルが高い? | 特に分電盤一体型は本体だけでも数万円するため、躊躇されがち。大規模な工事が必要であればなかなか決められない。 |
地震後の通電火災を防ぐには、感震ブレーカーの設置が効果的です。しかし費用や認知度の低さから普及が進んでいません。特に建物全体を守る分電盤型は入居者任せにせず自動で電気を遮断できるため、オーナー様にとっては資産を守る重要な備えです。この機会に設置をぜひご検討ください。